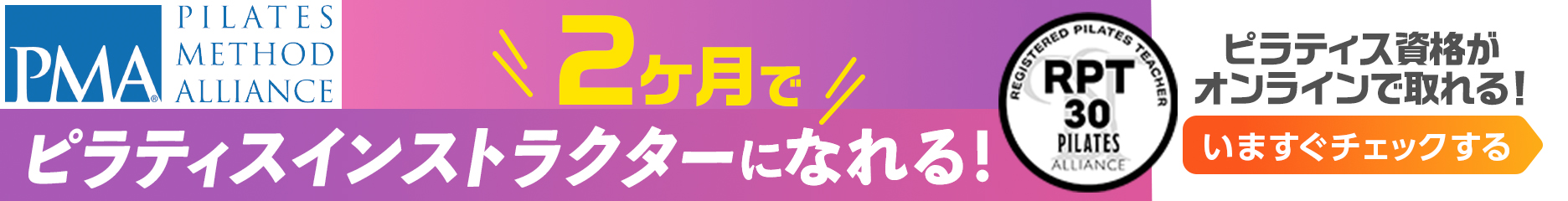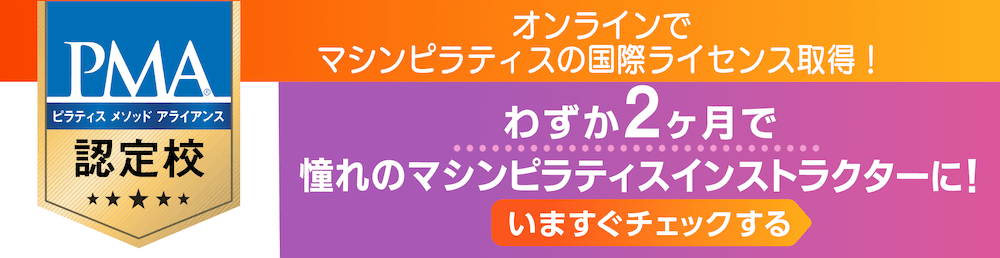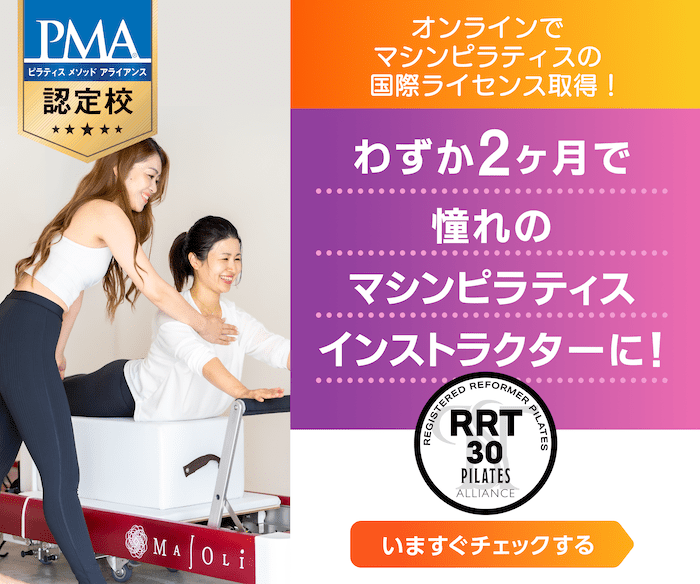ピラティスは姿勢が良くなると聞くけど、O脚も治るのか?そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
スタイルが良く見えるまっすぐな美脚を目指して、ピラティスに通っている方も増えてきています。
O脚は見た目でのコンプレックスでお悩みの方が多いですが、O脚のままでいると、実は将来の健康にも繋がってくるんです。
本記事では、O脚の原因やデメリットから、ピラティスは効果的なのか?まっすぐの美脚になるためのピラティスのエクササイズをまとめて解説いたします。
目次
O脚の原因って何?
立った時に膝がくっつかないでまっすぐな足にならず、コンプレックスに感じている方も多いでしょう。
そもそも、O脚になってしまう原因は、一体何なのでしょうか。
その大きな原因は、骨盤の歪みが原因といわれています。
骨盤は身体の中心にあり、O脚の人は、この骨盤が後ろに傾いている「後傾」の状態にあることが多いです。
そして、この状態になるまで以下のことが原因と考えられます。
- 姿勢が悪い:日々、生活する上で重心が偏った姿勢を取ったりしている
- 筋力が低下している:内転筋や体幹の筋力が低下している
- 遺伝的要因:骨格の形状、成長過程での影響を受けている
O脚でお悩みの方へヒアリングしてみると普段から無意識にしている姿勢が悪くなっていたり、仕事柄、どうしても姿勢が悪くなってしまっていがちになっている方が多く見受けられます。
また、ハイヒール、硬い靴などを長時間履き続けることにより、足のバランスが崩れていき、O脚へと進行させてしまうでしょう。
O脚になりやすい人の特徴
O脚になりやすい人は、骨盤の後傾の他にも様々な要因が考えられます。
O脚になりやすい人にも特徴があります。どんな特徴があるか詳しく説明していきます。
骨盤が後ろに傾きやすい(骨盤後傾)
骨盤が後に傾くと、股関節は外側にねじれてしまい、O脚になりやすくなってしまいます。
骨盤がなぜ後ろに傾いてしまうのか。
それは、太ももの裏側にある筋肉「ハムストリングス」(もも裏の筋肉)がかたいためです。
ハムストリングスのストレッチをすることによって、筋肉の柔軟性が高まってきます。
また、上半身と下半身をつなぐ筋肉「腸腰筋」の筋力低下も骨盤が後ろに傾いてしまう原因です。
この「腸腰筋」の筋力UPすることで、骨盤が後ろに傾いているのを前に傾きます。
骨盤を正常な位置に戻すには、「腸腰筋」のトレーニングも必要となってくるでしょう。
そのトレーニングとは、例えば、股関節と膝関節を90度曲げて座るなどがあります。
このトレーニングでインナーマッスルが鍛えられます。
お尻の筋肉がかたい(股関節が外旋しやすい)
お尻の筋肉がかたくなってくると足が外向き(外側)に引っ張られ、股関節が外側にねじれる(外旋する)原因となります。
運動不足や姿勢の悪さもお尻の筋肉は、かたくなりやすいですが、
デスクワークなどで、日頃から長時間同じ姿勢をしてしまう方も、かたくなりやすいといわれています。
お尻の筋肉をほぐすストレッチを頻繁に行いましょう。
また、股関節が外向きだけではなく、内向き(内側)でO脚になるケースもあるため、この特徴が一概とは言えません。
太ももの内側の筋肉が弱い(内転筋)
実は、日常生活だと鍛えにくい、太ももの内側の筋肉「内転筋」。
この、「内転筋」の筋力が低下していると足が閉じにくくなり、O脚になりやすくなります。
「内転筋」は、日常生活ではほとんど使うことがないといわれています。
内転筋は足を閉じたり、内側に寄せる働きがあり、骨盤を安定させるという大きな役割を果たしています。
綺麗な姿勢や体型を保つには、とっても大切な筋肉のため、O脚を治していくためにも、ぜひ、この「内転筋」のトレーニングをしていきましょう。
O脚のデメリット
O脚のデメリットは、見た目でのコンプレックスになってしまう問題もありますが、実は、体にも負担がかかっているんです。
O脚でいることの体への影響やデメリットを解説していきます。
足の外側に筋肉がつきやすくなる
足の外側に筋肉がついていると、足の太さも気になってきます。
これは、O脚によって足の重心が足の小指側(外側)にかかっている状態が原因です。
このため、足の外側の筋肉が張りやすくなり、外側に筋肉がつきやすくなります。
腰痛につながる
O脚の人は、腰痛を患いやすいといわれています。
骨盤が後に傾いていることから、この歪みを体のバランスが崩れて無理にバランスをとろうとしてしまいます。
すると、骨盤周辺の不可が大きくなり、腰痛へとつながってしまうことがあります。
むくみや疲れやすくなる
骨盤が後ろに傾き、股関節がねじれて内股になってしまいます。
この状態になると、血管やリンパ管が圧迫され、血液やリンパの流れが悪くなり、体のめぐりの低下へとつながります。
すると、体の中の老廃物が溜まりやすくなり、むくみやすくなります。
また、O脚の人は重心が外側になりバランスが悪くなると、血行不良を引き起こし、体が疲れやすくなるといわれ、さらに重心が外側になり足の外側ばかりの筋肉を使うと、足の疲れやすさにつながります。
変形性膝関節症のリスクが高くなる
O脚は膝の関節に負担がかかります。
膝に負担がかかると「変形性膝関節症」を発症するリスクが高まります。
この「変形性膝関節症」は、膝にある軟骨が少しずつすり減っていき、痛みを引き起こしてしまう疾患です。
今は大丈夫でも、じわじわとすり減っていくため将来的に「変形性膝関節症」の症状がでてくる可能性があります。
O脚でいることが、ここまで体に負担がかかっているとは驚きますよね。
早めに対策して、改善していくのがいいでしょう。
ピラティスでO脚は治るのか
O脚には様々な要因があることがわかりましたが、ピラティスでO脚は治るのでしょうか。
結論、治る可能性があるタイプ、治らないタイプの2つのタイプがあるんです。
- 治る可能性があるタイプ:後天性の場合
- 治らないタイプ:先天性の場合
それぞれ詳しく解説していきます。
後天性の場合
後天性の場合、改善できる可能性があります。
- 日常生活での姿勢が悪い(足組みや片足に重心をかける)
- 筋力の低下
- 体の柔軟性の低下
ピラティスは後天性へのO脚の改善には効果的であるということがわかります。
先天性の場合
先天性の場合、ピラティスでの改善は難しいケースが多いです。
先天性のO脚は以下のような要因です。
- 生まれつき骨に歪みがある
- 発育不全で骨に異常がある
- 靭帯にゆるみがある
- 骨や軟骨に疾患がある
特にO脚の中でも臼蓋形成不全の場合は、ピラティスでの改善は困難とされており、医療機関への相談をしたほうがいいでしょう。
ピラティスがO脚の改善に効果的な理由
では、なぜピラティスがO脚の改善に効果的なのでしょうか。
その理由を解説していきます。
筋力がアップする
ピラティスの動きは、足や骨盤周りの筋肉が鍛えられるエクササイズが多く、筋力のバランスが整います。
骨盤を支える筋力が低下すると、骨盤の歪みにつながります。
そのためにも、O脚改善には筋力をアップさせることが大切になります。
体の歪みを整える
ピラティスでインナーマッスル、体幹を鍛え、骨盤が正しい位置に戻ります。
さらに猫背や反り腰の改善効果も期待でき、体の歪みを整えることにより、左右のバランスも安定するため綺麗な姿勢を保てるようになります。
ピラティスを行い、正しい姿勢、重心をとれるようになれば普段の生活でも意識しコントロールができるようになり、常に綺麗な姿勢でいられるようになるでしょう。
ピラティスを続けていたら、姿勢が良くなって健康診断で身長が3cmも伸びて嬉しかったというお話もあったります。
柔軟性が向上する
エクササイズの中には、ストレッチを組み込んだ動きも幅広くあります。
そのため、体の柔軟性が向上します。
ピラティスで柔軟性をUPし、かたくなっていた股関節などの関節の可動域を広げていくことによりO脚改善へとつながります。
また、柔軟性が向上すると、ケガのリスクも軽減しやすくなります。
筋力アップ、体の歪みがとれ、柔軟性も向上するとO脚改善の他にも日常生活においてもピラティスの動きを意識するようになり、体や心にとってもプラスになることが重なってきます。
O脚も改善して、体や心も安定してくるならピラティスで理想的な健康が手に入れられるともいえます。
O脚改善に効果が期待できるピラティスエクササイズ
ピラティスのエクササイズの中でも、O脚への改善に効果が期待できるエクササイズを紹介します。
自宅でもできるマットピラティス、リフォーマーを使ったマシンピラティスのエクササイズをまとめました。
マットピラティス
サイドライイング・レッグリフト
横向きの姿勢で行う初心者向けエクササイズ。内転筋に効果的で足のラインが内側から整ってきます。
ブリッジ
寝た状態で行えるため、初心者におすすめのエクササイズです。大臀筋、内転筋郡へアプローチします。
マシンピラティス
フットワーク
足全体の筋肉を鍛えられ、大臀筋、内転筋、ハムストリングにアプローチします。
レッグ・サークル
股関節の分回し運動で、股関節をほぐします。
ピラティスでまっすぐ美脚を手に入れよう
ピラティスでは、日常生活が原因で骨盤が歪んでしまったり、筋力の低下、体がかたくなってしまっていることでのO脚を治すことが期待できることがわかりました。
O脚でお悩みの方、ぜひ自宅でできるエクササイズからはじめていき、O脚を改善、まっすぐ美脚を手に入れましょう。
また、将来の理想的な健康のためにも続けてみてはいかがでしょうか。
ピラティスを継続していくうちに、体の使い方もわかってくるようになるため、より意識し、普段の生活においても正しい姿勢が保てるようになるでしょう。